- 不安で何度も確認をしてしまい、
悩んでいる方へ - 具体的な症状
- 不安で何度も確認しまう原因
- 不安で何度も確認してしまう考えられる疾患
- 対処法
- 1日中不安を感じている・強い不安が
繰り返される場合には、お早目のご相談を
不安で何度も確認を
してしまい、悩んでいる方へ
 仕事のことや家庭のこと、学校・勉強のこと、お金のことなどで「不安」がまったくないという人はいません。ある不安が解消されても、生きている以上はまた新しい不安が生まれます。私たちは不安を和らげたり解消したりするために、さまざまな努力や工夫をし、バランスを保っています。
仕事のことや家庭のこと、学校・勉強のこと、お金のことなどで「不安」がまったくないという人はいません。ある不安が解消されても、生きている以上はまた新しい不安が生まれます。私たちは不安を和らげたり解消したりするために、さまざまな努力や工夫をし、バランスを保っています。
そういった中で、過剰な不安を抱えている、その不安に対して行き過ぎた行動をとってしまうといった場合には、不安障害などの疾患を疑う必要があります。
常に不安な気持ちで辛い思いをしている方、過剰な不安・不安を解消するための行動で日常生活に支障をきたしているという方は、お早目にご相談ください。
具体的な症状
翌日のプレゼンが不安だから準備をする、朝起きられるか不安だから目覚まし時計を2つセットするといったことは、物事に対しての正常な範囲で抱く不安、行動です。
もし、以下のような症状が見られる場合には、過剰な不安・行動と捉え、一度受診されることをおすすめします。
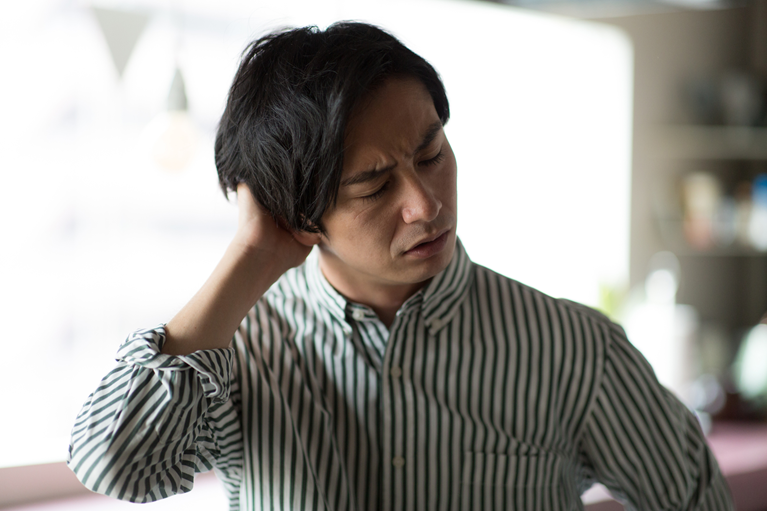
- 1日中、いつも不安、心配があり、落ち着かない
- 不安にさいなまれ、じっとしていることが難しい
- 突然、動悸・震え・呼吸困難・このまま死ぬのではないかという不安・めまい・吐き気などに襲われる
- 外出時、鍵を閉めたか不安で何度も家に戻って確認する(ガスの元栓、家電の電源なども含む)
- 手や身体、服が汚れているような不安がぬぐえず、繰り返し洗う
- 誰かが触ったと思うと不潔に感じられ、触れない
- 高所や駅のホームで、「このまま飛び降りてしまうのではないか」と不安になる
- ラッキーナンバー、不吉な数字に異様にこだわる、選べない・選んでしまった時に強い不安を感じる
- 家具、机の上の物を左右対称に置くことにこだわる、できない時に強い不安を感じる
- 特に根拠なく、誰かに危害を加えてしまったような気がして、ニュースなどで何度も確認する
- 自分の見た目、態度などが人を不快にさせている不安があり、そのことが頭から離れない
- レシートを受け取った時に金額に間違いがないか、何度も調べずにいられない
- 人前に出ること、喋ることなどに強い不安がある、そういった場面を避ける
- 人からどう見られているのかが不安で、いつもまわりの様子を窺っている
不安で何度も確認しまう原因
不安とは、私たちが生きていく上で必要な感情です。
不安を感じた時には、脳内でノルアドレナリン、アドレナリンといった物質が分泌され、集中力・判断力・心拍数・血流が一時的に上昇します。これにより、頭を使って問題を解決したり、身体を使って危険を回避したりする力を高めているのです。
ただ、実際には不安を抱くような状況ではないにも関わらず強い不安を感じてしまう場合、上記のような状態が長く続くため、心身のバランスが崩れやすくなるのです。
不安で何度も確認してしまう
考えられる疾患
社会不安障害
人前に出る・喋る・会食をするといった時に強い不安、恐怖、緊張を感じ、心身の症状が引き起こされます。また、そのような症状が出る場所や状況を回避しようとします。動悸や手足・声の震え、冷や汗、頭が真っ白になる、吐き気等の症状が見られます。
全般性不安障害
原因のよく分からない、漠然とした不安や心配が続きます。落ち着きがない・そわそわする、肩こり、不眠、めまいなどの症状を伴います。たとえば「元気にしている家族の健康を毎日のように心配する」など、一般的に言われる心配性という範囲を越えて不安・心配が認められます。
パニック障害
突然、原因不明の強い不安、恐怖感に襲われ、動悸やめまい、呼吸困難といった症状も伴います(パニック発作)。次にパニック発作が起こるのがおそろしく、電車やエレベーターなど閉鎖的な空間に入ることが難しくなることもあります。
強迫性障害
自分でも度が過ぎていると思いながら、不安な考え(強迫観念)を持ち、その不安を打ち消すための行為(強迫行為)を繰り返してしまうことを指します。鍵やガス栓の閉め忘れが不安で何度も確認しに戻る、手や身体が汚れている不安があり繰り返し洗うといたケースが典型例です。
不安障害
不安という気分が過敏になり、実際には危険・危機といえないものに対して強い不安を抱き、その不安を打ち消すために対策を講じる・回避しようとする障害の総称です。上記でご紹介した、社会不安障害、全般性不安障害、パニック障害、強迫性障害は、すべて不安障害に分類されます。
対処法
慢性的な不安、強い不安によってこころや身体が疲れているという時、日常生活に支障が出ているという時には、お早目に当院にご相談ください。
症状が軽いものであれば、以下のような対処法によって改善・解消することもあります。
趣味などに没頭する
何か好きなことに没頭しているあいだは、不安が和らぎます。ただ、それをやめたらすぐに同じ強さで不安が蘇ってきた、あるいは不安がチラついて没頭できないといった場合には、心療内科や精神科の受診をおすすめします。
適度な運動
 適度な運動も、手軽に不安、心配などを解消するのに役立ちます。運動をしたらスッキリして視野が開けたという経験は、多くの方がお持ちです。頭が整理されることで、不安の改善法・解消法が見つかるということもあります。
適度な運動も、手軽に不安、心配などを解消するのに役立ちます。運動をしたらスッキリして視野が開けたという経験は、多くの方がお持ちです。頭が整理されることで、不安の改善法・解消法が見つかるということもあります。
デジタルデトックス
スマホやパソコンでインターネットサイトを開く、SNSを見ると、必要のない情報が次々と目に飛び込んできます。有益な情報もありますが、それ以上の不安を煽る情報が入ってきますので、依存しないことが大切です。今やスマホは生活に欠かせないものとなっていますが、散歩の時に置いていく、ベッドに持ち込まない等の、プチデトックスから試してみることをおすすめします。
信頼できる人に相談する
 不安になった時の対処法、考え方などについて、信頼できる人に相談するというのもおすすめです。親身になってくれる人なら、話しているだけでもホッとしますね。不安について話すことで、ご自身の不安の感じ方が普通であるのか、もしくはそうでないのかを知るきっかけになることもあります。
不安になった時の対処法、考え方などについて、信頼できる人に相談するというのもおすすめです。親身になってくれる人なら、話しているだけでもホッとしますね。不安について話すことで、ご自身の不安の感じ方が普通であるのか、もしくはそうでないのかを知るきっかけになることもあります。
1日中不安を感じている・強い不安が繰り返される場合には、お早目のご相談を
 「不安」という言葉には、ネガティブなイメージがあります。ただこのページでもご紹介したように、危険や危機を察知し、頭を働かせて問題を解決する・危険から身を守ったりするために、一定程度は必要です。
「不安」という言葉には、ネガティブなイメージがあります。ただこのページでもご紹介したように、危険や危機を察知し、頭を働かせて問題を解決する・危険から身を守ったりするために、一定程度は必要です。
そのため、不安を感じることがあるからといって、過度に心配する必要はありません。物事に対して適度な不安を抱き、対策をたてたり訓練をしたりすることは、生活や人生をより良くしていくことにつながります。
しかし、日常生活に支障をきたすような強すぎる不安を抱き続けるのは、心身の健康を損ないます。不安が強い・続くことで疲れてしまった、人と比べて心配しすぎな気がするといった時には、お早目に当院にご相談ください。







