寝つきが悪い・
睡眠薬を飲まないと
不安で寝れない方へ
 寝つきが悪い、夜中に目が覚める、異様に早く目が覚める、睡眠時間はちゃんとあったはずなのに熟睡感がないといった症状がある方、睡眠薬を手放せなくなっているという方は、お早目に当院にご相談ください。
寝つきが悪い、夜中に目が覚める、異様に早く目が覚める、睡眠時間はちゃんとあったはずなのに熟睡感がないといった症状がある方、睡眠薬を手放せなくなっているという方は、お早目に当院にご相談ください。
このページでは、寝つきが悪い人の年代別の特徴、不眠症の原因・種類、対処法・治療法などについて解説していきます。
寝つきが悪い人の特徴
寝つきが悪い人に見られる特徴を、年代別でご紹介します。
10~20代
- スマホ、ゲーム、ネットへの依存傾向が見られる
- SNSに熱中している
- カフェイン入り飲料(近年ではエナジードリンクが多い)をよく飲んでいる
- 恋愛、友人関係のトラブルを抱えている
30~40代
- 仕事、家庭の両立を頑張っている
- 長時間労働をしている
- カフェイン入り飲料(コーヒーなど)をよく飲んでいる
- 経済的な不安を抱えている
- 運動習慣がほとんどない
- 職場、婚活、離婚などで悩んでいる
50~60代
- 更年期障害の症状がある
- 職場での責任が重い
- 親の介護問題、子どもの独立、将来の不安がある
70代~80代
- 日中の活動量、外出が減少している
- 配偶者、友人の死など辛い経験をした
- 経済的な不安がある
- 認知症と診断された
寝つきが悪い人の原因
 生活リズムの乱れ、ストレスなどが主な原因となります。
生活リズムの乱れ、ストレスなどが主な原因となります。
また、うつ病、不眠症、睡眠時無呼吸症候群、睡眠時隋半症、睡眠覚醒相後退障害などの疾患が原因となっていることも少なくありません。
不眠症の主な種類
不眠症は大きく、以下のように分類されます。
入眠障害
いわゆる、寝つきが悪い状態です。ベッドに入っても、30分~1時間程度、寝られません。
不眠症の中でもっとも多いのが、この入眠障害です。
中途覚醒
夜中に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか眠れないタイプです。
熟眠障害
睡眠時間は十分にとったはずなのに眠りが浅く、目覚めた時の熟睡感がありません。
睡眠時無呼吸症候群が原因になっていることもあります。
早期覚醒
朝、異様に早く目が覚めてしまい、二度寝ができないタイプです。高齢者、うつ病の方によく見られます。
対処法
クリニックで行うこと
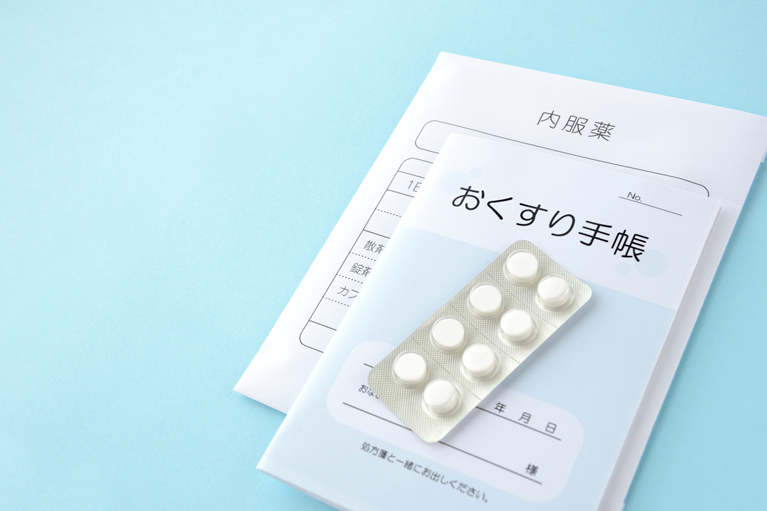 主に睡眠薬を用いる薬物療法、睡眠環境調整、生活習慣指導などを行います。
主に睡眠薬を用いる薬物療法、睡眠環境調整、生活習慣指導などを行います。
また、うつ病などの疾患を原因としている場合には、その疾患に応じた治療を行います。睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合には、連携医療機関をご紹介します。
寝つきを改善する為の自分でできること
デジタルデトックス
就寝の2時間前からは、スマホ、タブレット、パソコンなどの使用を控えましょう。少なくとも、ベッドには持って入らないようにします。
規則正しい生活を
取り戻す
休日を含め、起床時間・就寝時間をできるだけ一定にしましょう。
カフェイン・アルコールを控える
夜になってからのカフェイン、アルコールは控えましょう。アルコールを飲むと眠くなり、入眠はしやすくなりますが、夜中の中途覚醒の原因となります。
日中に十分に活動する・適度に運動をする
日中に適度に身体を疲れさせることは、睡眠の質の改善につながります。ただし、就寝前は激しい運動を控えてください。
睡眠環境を整える
寝室の室温は18~23℃、湿度は40~60%を目安に調整してください。ドアや窓を少しだけ開け、空気の入れ替えができるのが理想的です。
お風呂の入り方を見直す
就寝の1~2時間前に、ぬるめのお風呂に長めに浸かると、心身がリラックスして睡眠の質が改善します。
睡眠薬をやめるタイミング
 不眠症の治療では、主に睡眠薬を使用します。
不眠症の治療では、主に睡眠薬を使用します。
十分に眠れるようになり、服用を中止するのが目標ではありますが、自己判断での使用中止はお控えください。誤ったタイミングで急に使用をやめると、不眠の症状が強くなる・離脱症状が現れるということがあります。
医師の判断でやめる場合も、通常はゆっくりと時間をかけて、量を減らしていきます。
内服と並行して行う睡眠環境調整、生活習慣指導によって、少しずつ、お薬なしでも眠れるようになることが期待できます。
- 睡眠薬を減らしたい場合には、必ず医師にご相談ください。
- 自己判断で内服を中止する、減らす・増やすといったことはお控えください。
- お薬だけに頼らず、睡眠環境調整、生活習慣指導にも取り組みましょう。







